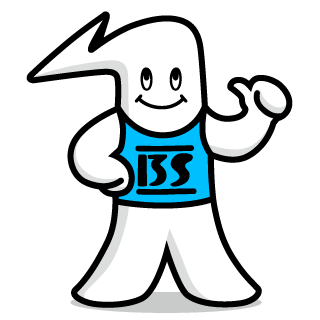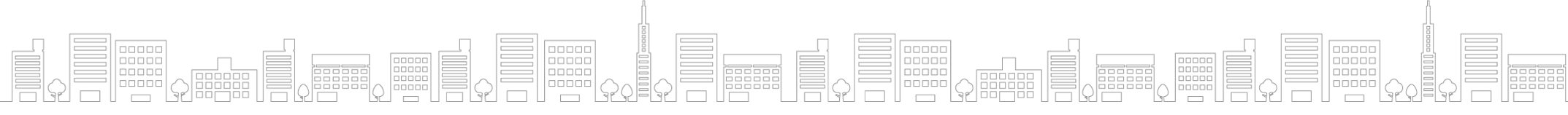10月です!下半期のスタートとなりました!
皆さん、こんにちは!
人事の大戸です!
すっかり私もBS人事通信の更新者として仲間入りしました。
そんな大戸がお送りする、今月のBS人事通信スタートです♪
先月、内定者に向けた職場見学を実施いたしました!!
先輩社員の生の声を聞いてもらうことや、社内の雰囲気を味わってもらうことは
BSグループの職場見学で欠かさずに行っています。
今まで多くの学生さんと職場見学を実施してきましたが、
社員へのインタビューで多かった質問が「やりがいを教えてください。」でした。
仕事のやりがいは、仕事のモチベーションにも繋がってくるので大切な役割があります。
◆今回のお題◆
「やりがい」
よく“あなたのやりがいは?”と聞かれることはありませんか。
やりがいとは、物事に対する充足感や手応えのことです。
「やりがいがある」という表現は、充足感や手応えを感じられる事柄に対して使われます。
やりがいは、仕事、趣味、人間関係といった様々な分野で感じることができますし、
一人ひとりの性格や価値観が異なるように、同じ労働環境で仕事をしていても、やりがいは人によっては異なります。
今回は仕事に対するやりがいについてお話します。
多くの人にとって仕事は「人生の大半を費やすもの」となっています。
長く働くならば、仕事にやりがいを感じながら楽しく働くほうがいいですよね。
そのために、仕事のやりがいを気にする人が世の中、とても多いです。
自分自身にとって満足度の高い人生を送るためには、周囲に振り回されず、
「自分にとってのやりがい」を見つけていくことが大切と言われています。
☆仕事でやりがいを感じるポイントは、大きく4つあります。
①仕事に対する充足感や達成感
②持っている知識や能力を発揮
③自身の成長
④自分のパフォーマンスに対しての対価(成果や評価、報酬など)
上記のどれに重きを置くかは個人差がありますし、必ずしも上記の感情のみが正しいわけではありません。
ですが、いずれにしても何かしらの感情が満たされていない状態の時に、人はやりがいを感じられなくなってしまいます。
☆仕事でやりがいを見つけるためにはどうすればいいのか。
大きなポイントは「自己分析」です。
「自分は日常生活や仕事においてどんなときに達成感や幸福感を感じることができるのか」自分の価値観を知ることが大切です。
たとえば、「人からほめられたとき」「成果を認められたとき」「目標を達成したとき」などが挙げられたとしたら、
そこから労働価値を見出していきます。
また、自分自身を客観的に見つめ直すことで、「何がしたいのか」「自分のやりがいとは何か」に気づくことができます。
このような流れで人は仕事のやりがいをみつけて、モチベーションを高めたり自分の存在意義を確認したりします。
しかし最近では、「やりがい搾取」
この言葉が人事領域でトレンドに上がってきています。
「やりがい搾取」とは、社員の“やりがい”のみで仕事をさせ、労働者の労働力や時間を奪い取ることをいいます。
「私でないと、この仕事はだめになってしまう」という、“やりがい”や“責任感”を与える一方で、会社の待遇は良くない。
といった通常、賃金は労働力や労働時間に対する対価として与えられますが、代わりに“やりがい”という
目に見えないものを与えて「労働力を使用する=搾取する」とつかわれていて近年では問題視されています。
やりがいを社員に与えるということは、きれいに聞こえますがふたを開けてみると、
社内環境は全く整えられていないような落とし穴がある場合があります。
「やりがい搾取」にならないために企業はしっかりと社内制度を改めて働き方や報酬、
組織体制などを見直すきっかけを与えることも大事とされています。
社員に仕事のやりがいを見つけ出させられるような仕事内容を提供することは、前月のBS人事通信でお話した
社員のエンゲージメントを高める・モチベーションを上げることに対して直結していくのでとても重要となっています。
しかし“仕事のやりがい”ばかり重きを置いてしまうと社内制度への不満や不安が出てきてしまいます。
そうならないように、バランスを取りながら社内の内部調整を行っていかないといけません。
BSグループで働く上での仕事のやりがいは、沢山あります。
しかし仕事のやりがいだけではなく、社内環境や制度を整えることが大切ということを
私たちBSグループもしっかりと把握していかないといけないと考えております。
皆さんも、“やりがい” とはなんだろうと自分を見つめなおして
自分にとって有意義な時間を過ごせるような人生にしていきませんか。
今回の記事はここまでです!
また、お会いできることを楽しみにしております!
それでは、次回もお楽しみに♪
======================
BSグループではInstagramで社内の様子やトピックスを更新中です♪
公式Instagram:@bsgroup_recruit